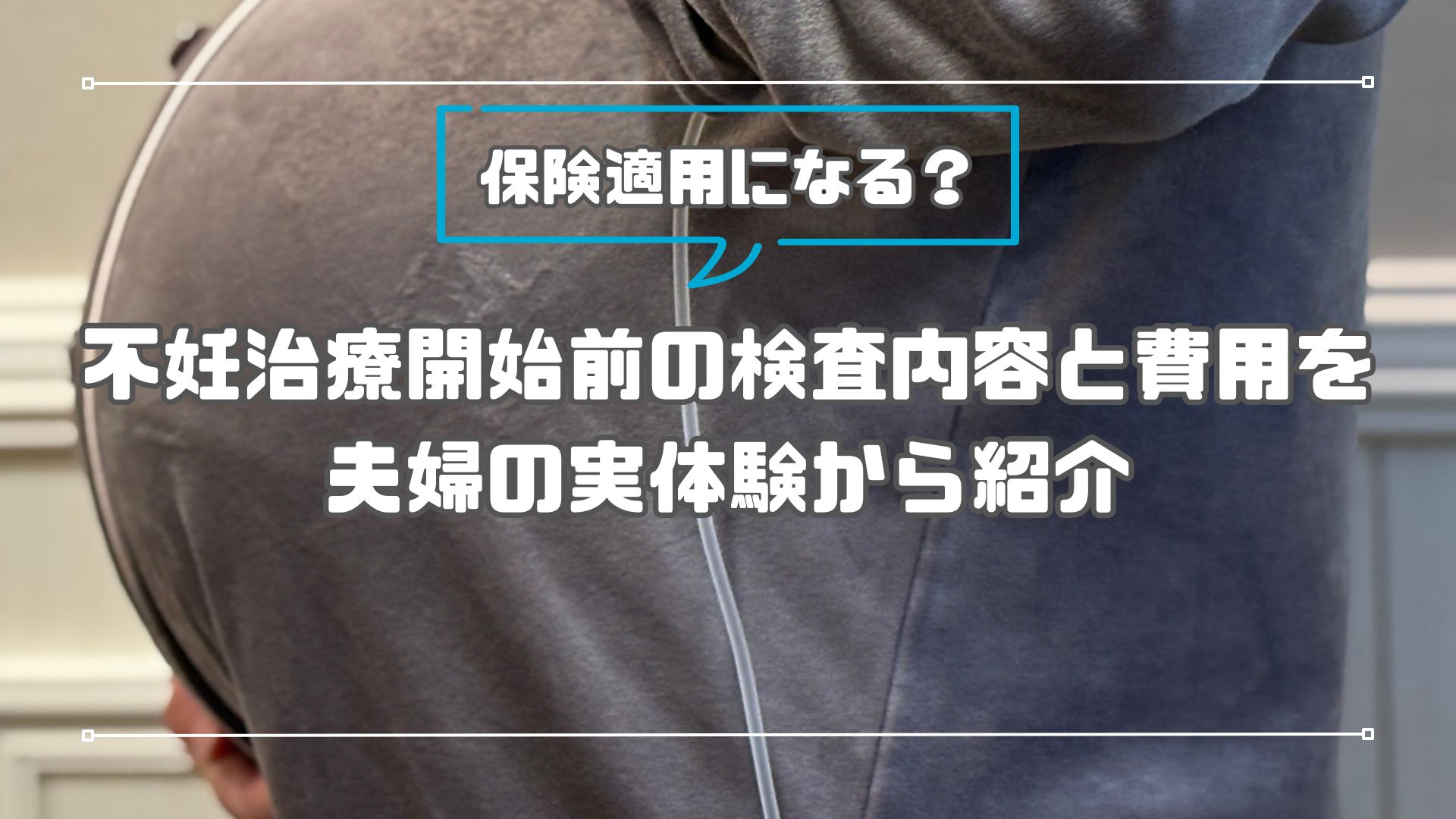不妊治療を開始するにあたり、あれこれ検査された双子のパパ・ナガトとママ・うさこです!
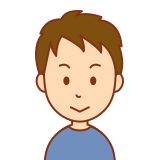
「治療計画」を立てるために夫婦の身体に妊娠しにくい原因がないかを検査しました。
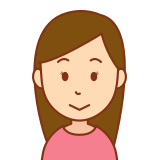
夫に比べて私のほうが検査項目が多かったな…
不妊治療を進めるにあたり、まずは夫婦の身体を検査し、それをもとに「治療計画」を立てるという流れでした。
男性の検査項目はそれほど多くありませんが、女性の検査は項目が多く、中には痛みを伴う検査もありました。
不妊治療を始めるにあたってどんな事から進めていくの?という点が気になる方は是非私達の経験を参考にしてみてください。
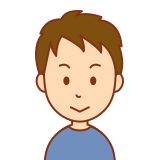
思い出しながら書いているので事実と異なる内容があるかもですが、参考まで!
それでは「保険適用になる?不妊治療開始前の検査内容と費用を夫婦の実体験から紹介」について書いていきます。
私達夫婦の検査内容と結果について
私達夫婦が行なった検査はそれぞれ次の通りでした。
ナガト(夫)の場合
精液検査、血液検査を行ったと記憶しています。
血液から色々調べたと思いますが、引っかかった項目が1つだけありました。
それは、風疹の抗体値が低かった事です。
医師からの指示でナガトは風疹のワクチンを接種しました。
風疹の抗体値が低いと、言わずもがな風疹にかかるリスクが高まります。
妊婦が風疹にかかると胎児にも影響が出るため、パートナーはもちろん、できれば祖父母も必要であれば摂取するべきでしょう。
接種後、風疹の抗体値が問題のない値になりました。
因みに精液検査もギリギリ自然妊娠できるくらいの数値だったため、生活習慣の改善やサプリメントの摂取をするよう言われました。
うさこ(妻)の場合
ナガトに比べてうさこは血液検査以外にも複数の検査を行いました。
周期に合わせて以下の様な検査を行ったと記憶しています。
・血液検査
・子宮卵管造影検査
・フーナーテスト
・超音波検査
これらの中でも、子宮卵管造影検査は痛みを伴う辛いものでした。
子宮卵管造影検査について説明しておくと、女性の子宮内腔の形態と卵管の通過性を調べる検査になります。
具体的には、以下のような異常がないかを確認します。
- 子宮の形態異常: 子宮奇形(単角子宮、双角子宮など)、子宮筋腫、子宮腺筋症による変形、子宮腔内の癒着、子宮内膜ポリープなど
- 卵管の通過性: 卵管の狭窄(狭くなっている)、閉塞(詰まっている)の有無、その場所
- 卵管周囲の癒着: 卵管や卵巣の周りに癒着がないか
- 卵管留水腫: 卵管に液体が溜まって嚢状になっている状態
など
これらの異常があると、精子と卵子が出会うことができなかったり、受精卵が子宮に到達できなかったりするため、妊娠しづらくなるそうです。
個人差はあるのですが、うさこはひどい生理痛のような痛みを感じました。
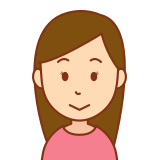
痛みに耐えられないことはないのですが、早く終わってくれ〜というような感覚でした。
費用
不妊治療開始前の検査の費用
不妊治療開始前の検査にかかった費用は夫婦で約4万円でした。
不妊治療の保険診療では、妊娠しにくい原因がないか調べる「スクリーニング検査」は保険適用外となるため、結構な費用がかかりました。
ただ、これはまだ序の口。
体外受精や顕微授精になると保険適用&高額医療費でもかなりの費用がかかってきます。
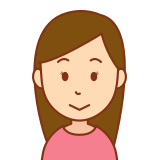
高額医療制度も使っていましたが、体外受精や顕微授精の際には月の支払いが新卒初任給くらいになることもありました。
出産時の出産一時金や、育児における児童手当などの制度はある程度充実しています。
一方で、不妊症の夫婦が子どもを作ることに対する手当と言うのはまだ殆どない様に見受けられます。
不妊治療が保険適用になる
2022年4月より、不妊治療の保険適用範囲が大幅に拡大されました。
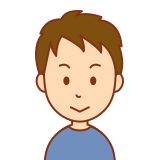
ちょうど私達夫婦が不妊治療を始めた時期だったので助かりました。
これにより、これまで高額な費用がかかっていた多くの治療が公的医療保険の対象となりました。
私達夫婦もタイミング法から体外受精、顕微授精もしましたが、それらも基本は保険適用の対象だったため、経済的負担が大きく軽減されました。
保険適用となる不妊治療の種類
保険適用となる不妊治療の種類は、大きく分けて以下の2つに分類されます。
- 一般不妊治療
- タイミング法: 排卵日を予測し、性交のタイミングを指導する方法
- 人工授精 (AIH): 排卵の時期に合わせて、精液を直接子宮内に注入する方法
- 生殖補助医療 (ART: Assisted Reproductive Technology)
- 体外受精 (IVF): 体外で卵子と精子を受精させ、得られた胚を子宮に戻す方法
- 顕微授精 (ICSI): 卵子の中に直接精子を注入して受精させる方法
その他、これらの治療に関連するさまざまな項目が保険適用となっています
保険適用の対象者と条件
保険適用の対象者と条件は以下の通りです。
- 年齢制限(生殖補助医療のみ)
- 治療開始時点の女性の年齢が43歳未満であること
- 40歳未満の場合:1子ごとに通算6回まで胚移植が可能
- 40歳以上43歳未満の場合:1子ごとに通算3回まで胚移植が可能
- タイミング法や人工授精には年齢制限、回数制限はありません
- 男性の年齢による制限はありません
- 回数カウントの例外:
- 胚移植の回数でカウントされ、採卵の回数は含まれません
- 保険適用外の治療や過去の助成金を利用した治療の回数は、上記の回数にはカウントされません
- 出産に至った場合、回数はリセットされます
- 治療開始時点の女性の年齢が43歳未満であること
- 婚姻関係(事実婚も対象)
- 法律上の婚姻関係にある夫婦だけでなく、事実婚のカップルも対象となります。ただし、事実婚の場合は、出生した子について認知を行う意向があるなど、別途要件を満たす必要があります。
- 治療計画
- 医師から治療計画について十分な説明を受け、患者本人とそのパートナーが同意している必要があります。
- その他
- 日本の公的医療保険制度に加入している必要があります。
先進医療との併用
原則として、保険診療と自由診療(全額自己負担の診療)を併用する「混合診療」は認められていません。
しかし、不妊治療においては厚生労働省が認めた医療技術に限り、保険診療との併用が可能です。
先進医療の費用は全額自己負担となりますが、それに付随する保険診療部分には保険が適用されるため、経済的負担を軽減しながら、より高度な治療を受けることが可能になります。
ただ、私達夫婦は先進医療を併用することはありませんでした。
治療計画においても一部先進医療を進められましたが、やっぱり費用が高額だったため断念しました。
このあたりの詳細は治療を開始すると病院から説明もあると思うので、治療計画のタイミングなのでよく確認してみたほうが良いでしょう。
高額療養費制度の適用
保険適用された不妊治療の費用は、高額療養費制度の対象となります。
これにより、ひと月の医療費が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が払い戻されます。
ただし、払い戻しには結構時間がかかります。
不妊治療を始めるならなるはやで高額療養費制度の申請をしておくことをおすすめします。
手続きが完了していれば、病院の支払い窓口で医療費の自己負担額が一定額を超えた分を計算して請求してくれます。
まとめ
本記事は「保険適用になる?不妊治療開始前の検査内容と費用を夫婦の実体験から紹介」について書きました。
以下に内容をまとめます。
検査内容と費用
- 男性:主に精液検査と血液検査が行われます。筆者の夫は風疹の抗体値が低く、ワクチン接種が必要でした。妊婦が風疹にかかると胎児に重篤な影響が出る可能性があるため、パートナーのワクチン接種は重要です。
- 女性: 血液検査のほか、子宮卵管造影検査、フーナーテスト、超音波検査など、男性より多くの検査があり、子宮卵管造影検査は痛みを伴う場合があります。これらの検査で、子宮や卵管の異常がないかを確認します。
- 費用: 治療開始前の検査費用は夫婦で約4万円かかりました。これは「スクリーニング検査」が保険適用外のためです。
不妊治療の保険適用
- 2022年4月から不妊治療の保険適用範囲が大幅に拡大され、経済的な負担が軽減されました。
- 対象となる治療: タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精などが含まれます。
- 適用条件: 生殖補助医療には、治療開始時の女性の年齢が43歳未満という年齢制限(40歳未満は1子ごとに6回、40歳以上43歳未満は3回まで胚移植可能)があります。また、法律上の婚姻関係または事実婚であること、医師との治療計画への同意、公的医療保険への加入が必要です。
- 先進医療との併用: 原則として混合診療はできませんが、厚生労働省が認めた先進医療に限り、保険診療との併用が可能です。先進医療部分は全額自己負担ですが、付随する保険診療部分には保険が適用されます。
- 高額療養費制度: 保険適用された不妊治療費は高額療養費制度の対象となり、自己負担限度額を超えた分は払い戻されます。ただし、払い戻しには時間がかかるため、早めの申請が推奨されています。
以上、ナガト・うさこでした!